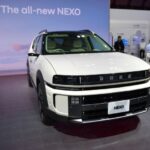豊田合成、小型FCVコンセプト初公開。着脱式で水素利用の拡大へ【JMS2025】
会員限定記事
2025/11/12(水)
ジャパンモビリティーショー2025(以下、JMS2025)では、水素エンジンや水素トラック、さらには家庭用エネルギーとして水素を活用する模型など、多様な展示が行われた。政府も2024年5月に水素社会推進法を成立させ、水素供給拠点の整備を後押しするなど、官民一体で水素社会の実現を進めている。
一方で、水素の汎用性にはまだ不透明な部分も多く、特に電気と比較すると現時点での応用範囲は限られている。こうした中で、豊田合成は水素の新たな可能性を提示するコンセプトモデルを披露し、来場者の注目を集めた。
一方で、水素の汎用性にはまだ不透明な部分も多く、特に電気と比較すると現時点での応用範囲は限られている。こうした中で、豊田合成は水素の新たな可能性を提示するコンセプトモデルを披露し、来場者の注目を集めた。