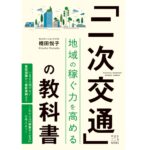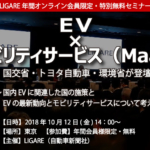名古屋SRTが拓く都市の未来:戦略的インフラが牽引する新たな価値創造
法人プレミアム会員限定記事
2025/7/7(月)
名古屋の都心風景が今、大きな変革期を迎えている。リニア中央新幹線の開業やアジア・アジアパラ競技大会の開催を控え、名古屋市は魅力あふれる都市への成長を目指し、さまざまな取り組みを進めている。その中核を担うのが、名古屋市独自の新たな路面公共交通システム、SRT(Smart Roadway Transit 以下:SRT)である。SRTは単なる移動手段ではなく、都市の景観と一体となり、まちの回遊性向上と賑わい拡大を図ることを目的としている。
5月10日、まちづくり講演会「名古屋の都心風景が変わるSRTとまちづくり」が開催された。当日は名古屋市によるSRT計画の説明に続き、株式会社GKデザイン...
5月10日、まちづくり講演会「名古屋の都心風景が変わるSRTとまちづくり」が開催された。当日は名古屋市によるSRT計画の説明に続き、株式会社GKデザイン...
※このコンテンツは法人プレミアム会員様限定公開です。会員の場合はログインしてください。
無料会員および有効期限切れの場合は以下のページから法人プレミアム会員にお申し込みください。
年間スタンダード会員の方はこちらのお問い合わせから法人プレミアム会員にアップグレードしてください。
無料会員および有効期限切れの場合は以下のページから法人プレミアム会員にお申し込みください。
年間スタンダード会員の方はこちらのお問い合わせから法人プレミアム会員にアップグレードしてください。