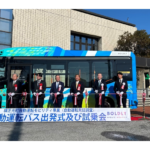【特集】国交省 鶴田総合政策局長に聞く 対話重視の交通空白解消と自動運転
会員限定記事
2025/10/28(火)
国土交通省が国内の「交通空白解消」に取り組んでいる。2024年7月に発足した、国交相を長とする、「『交通空白』解消本部」は「地域公共交通のリ・デザイン」を通じて「地域の足」「観光の足」の充実を狙う。省・国内各地の運輸局と自治体、事業者が強く連携する中で、自動運転にかかる期待も当然大きい。これまで「リ・デザイン」や自動運転を推進し、「交通空白」解消本部も立ち上げてきた国交省 総合政策局の鶴田浩久 局長に、自動運転の実装支援や空白解消について聞いた。
鶴田浩久(つるた・ひろひさ)氏 国土交通省 総合政策局 局長
経歴:1990年運輸省(現国交省)入省、国交省の発足以来、航空ネットワーク部...