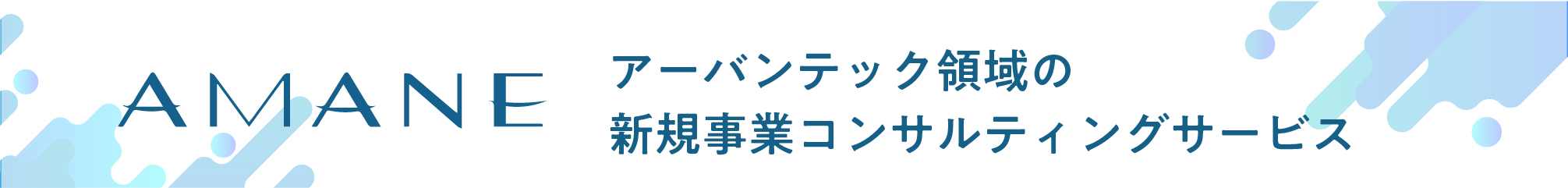シェアリング・エコノミー×自動運転がもたらすものとは?株式会社ティアフォー 取締役 加藤 真平 氏 インタビュー
会員限定記事
2017/3/1(水)
加藤真平氏
東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
名古屋大学未来社会創造機構 客員准教授
(株)ティアフォー取締役
2008年に慶應義塾大学大学院理工学研究科で博士(工学)を取得。その後、東京大学、カーネギーメロン大学、カリフォルニア大学サンタクルーズ校を経て、2012年より名古屋大学、2016年より東京大学に勤務。オペレーティングシステム、リアルタイムシステム、並列分散システムに関する研究に従事。特にメニーコアCPU、GPGPU(General-purpose computing on graphics processing units:GPUの資源を画像処理以外の...