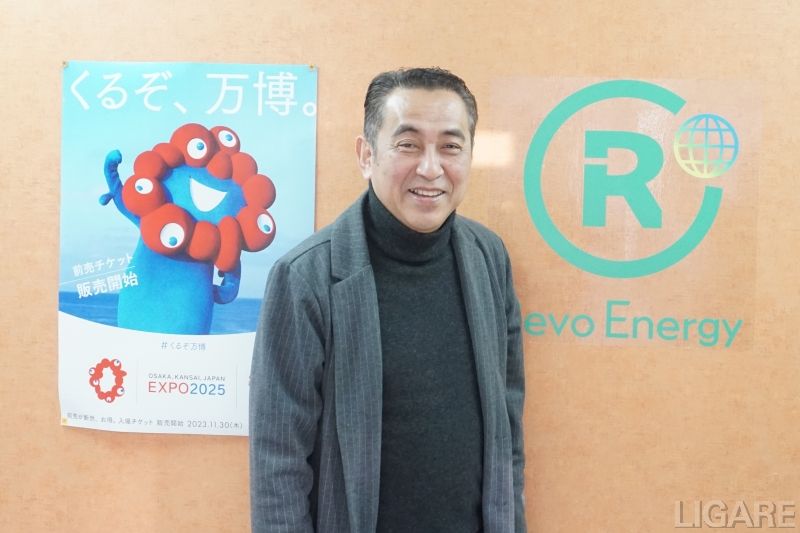ミドリムシと稲から作る次世代バイオ燃料―大阪発企業が目指す「自給自足」システムとは?―
会員限定記事
2025/4/3(木)
運送業の脱炭素化を背景に導入が進むEVやFCVと並び、期待されているのがバイオ燃料の利用だ。しかしながら、ガソリンの代替となるバイオエタノールも、軽油の代替となるバイオディーゼルも、従来の製造方法には原料調達など幾多の問題点があるという。
その問題点を打破する可能性を持つのが、大阪府に拠点を置くRevo Energyだ。2022年設立の同社は、ミドリムシと稲を組み合わせた画期的な方法でバイオディーゼルの開発に成功。物流大手らと組んだコンソーシアムでの実証や、大阪・関西万博への出展を経て、今後のさらなる拡大を見据えている。
同社の代表を務める中谷敏也氏が語る、従来の常識を覆す「自給自足」型の燃料プラントとは?インタビューを通じて、その構想と取り組みに迫る。
その問題点を打破する可能性を持つのが、大阪府に拠点を置くRevo Energyだ。2022年設立の同社は、ミドリムシと稲を組み合わせた画期的な方法でバイオディーゼルの開発に成功。物流大手らと組んだコンソーシアムでの実証や、大阪・関西万博への出展を経て、今後のさらなる拡大を見据えている。
同社の代表を務める中谷敏也氏が語る、従来の常識を覆す「自給自足」型の燃料プラントとは?インタビューを通じて、その構想と取り組みに迫る。
■運送事業者を悩ませる3つの課題解決に向けて
——まずは、Revo Energyが取り組む事業について教えてください。中谷氏:私たちは、ミドリムシ(ユーグレナ)を使ったバイオディーゼル(軽油の代替燃料)の普及に取り組んでいます。事業を通じて、運送業界の課題解決に貢献しようと考え、Revo Energyを立ち上げました。
――御社から見て、現在の運送業界にはどんな課題があると考えていますか?
中谷氏:3つの大きな課題があると考えています。まず燃料価格の高騰、次に「2024年問題」とも呼ばれていた人手不足、そして環境問題への取り組みです。
——それらの課題解決にアプローチする御社の技術について教えてください。
中谷氏:私たちのコア技術は、高効率なミドリムシ培養と、培養に欠かせない特殊な稲の栽培に関するノウハウです。これらの優位性を生かして、バイオディーゼルを原料から自給自足できる小型プラントの構築に取り組んでいます。
――自給自足のプラントとは、どんな仕組みでしょうか?
中谷氏:具体的には、ミドリムシの餌となる培養液を稲から作り、その培養液でミドリムシを増やします。そして、培養したミドリムシの油脂から軽油の代替燃料となるHVO※を精製する。これらの一連の流れをプラント内で完結させる仕組みです。
※HVO:水素化処理油。Hydrotreated Vegetable Oilの略。植物油、廃食油または動物性油脂から水素化精製法によって精製したバイオディーゼルの一種。(参照:国交省「船舶におけるバイオ燃料取り扱いガイドライン」)
——自給自足の手法を構築する背景には、従来のバイオ燃料における課題があるのでしょうか?
中谷氏:そうですね。全てのバイオ燃料に共通する最大の課題は、原料調達です。環境問題を背景に期待されている燃料である一方で、例えばバイオディーゼルの主な原料である廃食油が不足して争奪戦になっています。しかも取引価格が高騰しており、廃食油をかき集めるよりも、食用油メーカーから直接買った方が安いのでは、と思えるほどです。
そのほかにバイオディーゼルの原材料として利用されるパーム油(ヤシ油)に関しては自然破壊を防ぐ観点から輸入規制がかかっています。また、ガソリンの代替燃料であるバイオエタノールの原料となるサトウキビなどの作物は、食品利用と競合してしまいます。
対して、自給自足の小型プラントであれば外部環境の影響を受けないので、材料調達や燃料確保を安定させることが可能です。