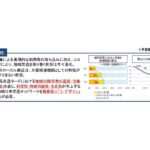【特集】自動運転実装の最前線 国交省 物流・自動車局 笹本氏「事業化と制度整備急ぐ」
会員限定記事
2025/8/27(水)
2025年度目途に国内50カ所程度でのサービス提供を目指し、普及が進む自動運転。国土交通省 物流・自動車局は自動運転の普及に向けて司令塔の役割を担う。局 自動運転戦略室 自動運転技術審査官(インタビュー当時)を務める笹本翔氏は国内で実証実験が行われ始めた時期から制度の設計を担っている。日本の自動運転の発展を実務で支える氏に社会実装の現状と今後の展望を伺った。
笹本翔(ささもと・しょう)氏
経歴:2009年国土交通省入省。国産旅客機スペースジェット(旧MRJ)の安全認証審査や、自動車関連の制度などの海外展開、省全体の科学技術政策の企画立案・総括、公道での自動運転を可能とした道路運送車両...