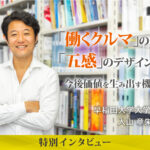【特集】鉄道と自動車に精通した研究者が語る自動運転とMaaSの展望―須田義大教授インタビュー
会員限定記事
2025/9/4(木)
鉄道と自動車の垣根を越えて研究を続けてきた須田義大教授(現 東京工科大学 片柳研究所教授・未来モビリティ研究センター長)は、それぞれの分野で進む自動運転の普及について、“ある問題点”を指摘する。現在も両分野の第一線を走る同氏だからこそ見える課題、そしてモビリティ社会の変革につながる道筋を聞いた。
鉄道と自動車それぞれの第一線で走り続けたこれまで
――須田教授の研究領域は、鉄道と自動車の両者にまたがっています。どのような経緯でこれまで取り組んできたのでしょうか?大学院の修士課程で当時は「車両工学」と呼ばれていたモビリティの研究を始め、最初は鉄道車両などのハードウエアに関する研究をして...