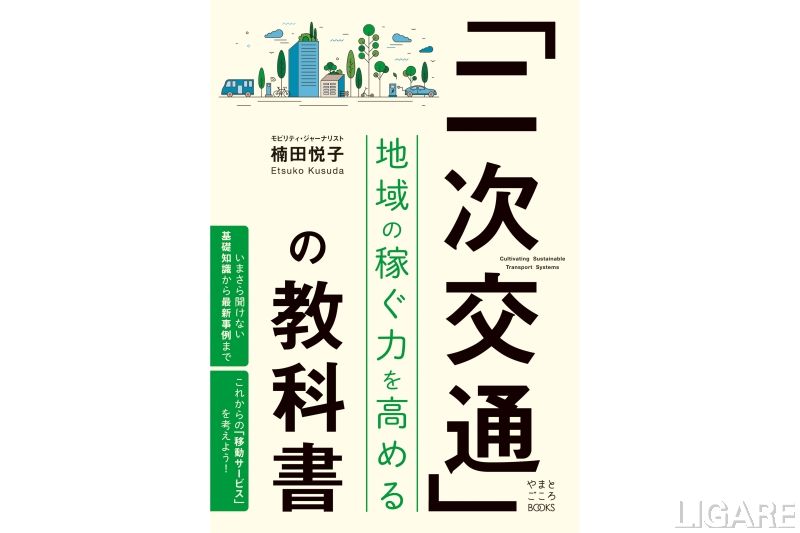【選書】観光と交通の架け橋となる実践的ガイド/『二次交通の教科書 地域の稼ぐ力を高める』
法人プレミアム会員限定記事
2025/5/9(金)
モビリティ・ジャーナリストの楠田悦子氏が執筆した『二次交通の教科書 地域の稼ぐ力を高める(以下、本書)』は、地域の観光振興と交通課題に対して当事者目線で向き合った実践的ガイドブックだ。本書に盛り込まれた知識や事例の数々は、持続可能なまちづくりを考える人々に新たな知見と未来への希望をもたらしてくれるだろう。
観光と交通の分断という課題
「二次交通」とは、拠点となる空港や鉄道の駅から観光地までの交通のこと※を指す。過疎化などを背景に、多くの地方都市において大きな課題となっている。※引用:株式会社JTB総合研究所 用語集
本書の冒頭で楠田氏は、観光分野と交通分野における双方の連携不足を指摘する。例えば多くの自治体において、両分野に別部門で取り組んでいることからも、この指摘に頷ける人は多いだろう。
こうした背景から、本書の読者層は「DMOや自治体担当者、観光事業者、地域・まちづくり関係者、交通事業者」を念頭に置く。「観光客を呼び込みたいけれども、移動手段がない」という地域に向けた実践的な内容となっている。「既存の公共交通の構造や問題点、新しく登場してきた移動手段やサービスの基本的なことを知ること」と「ツールとして移動手段をどんどん使い、地域活性化に繋げていくこと」。この二段構えのアプローチが重要だと楠田氏は説く。
※このコンテンツは法人プレミアム会員様限定公開です。会員の場合はログインしてください。
無料会員および有効期限切れの場合は以下のページから法人プレミアム会員にお申し込みください。
年間スタンダード会員の方はこちらのお問い合わせから法人プレミアム会員にアップグレードしてください。
無料会員および有効期限切れの場合は以下のページから法人プレミアム会員にお申し込みください。
年間スタンダード会員の方はこちらのお問い合わせから法人プレミアム会員にアップグレードしてください。